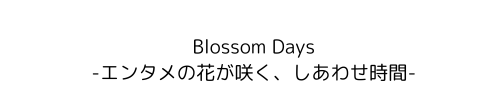※当サイトはプロモーションを含みます
はじめに:九州に熊はいないって本当?

登山やキャンプを楽しむ人にとって「熊対策」は重要なテーマですが、九州では「熊鈴不要」と言われるほど、野生の熊がいない地域として知られています。
しかし、かつて九州にもツキノワグマが生息していたことをご存じでしょうか?
この記事では、熊が九州にいない理由、いつまでいたのか、そして近年の目撃情報までを徹底的に解説します。
熊はいつまで九州にいた?最後の記録と絶滅宣言
九州におけるツキノワグマの最後の記録は、1941年に大分県と宮崎県の県境付近で確認された子グマの腐乱死体です。
その後、1987年には大分県の祖母・傾山山系でオスのクマが捕獲されましたが、遺伝子解析の結果、本州北陸地方から移入された個体であり、九州固有のクマではないことが判明しました。
環境省は2012年に「九州産ツキノワグマは絶滅」と正式に宣言しています。
つまり、九州に野生の熊が自然分布として存在していたのは、20世紀前半までと考えられています。
熊が九州にいない理由とは?絶滅の背景を探る
熊が九州から姿を消した理由は、以下のような複合的な要因が挙げられます。
1. 森林伐採による生息地の消失
江戸時代から明治にかけて、人口増加や産業発展に伴い、田畑や集落が拡大。
燃料や製鉄用の木材伐採も進み、クマが暮らす原生林が激減しました。
2. 狩猟と駆除の影響
クマは農作物を荒らす害獣、また人を襲う危険な存在として狩猟や駆除の対象となり、鉄砲や罠の発達により急速に数を減らしました。
3. 島としての地理的要因
九州は本州と海で隔たれているため、一度個体数が減ると自然に補充されにくい環境でした。
本州からの移入が困難で、孤立した生態系が絶滅を加速させたと考えられています。
🧬 ツキノワグマの遺伝的特徴と九州個体群の違い
ツキノワグマ(Ursus thibetanus)は、アジア全域に広く分布する中型のクマで、日本では本州・四国・九州にかつて生息していました。
その遺伝的特徴は、ミトコンドリアDNA(mtDNA)のDループ領域の解析により、以下の3つの系統に分類されることがわかっています:
- 東部クラスター(東北地方など)
- 西部クラスター(中部・近畿地方)
- 南部クラスター(四国・紀伊半島)
九州個体群は“西部クラスター”に属していた
2023年の研究では、九州で発見された古い骨試料(4点)を解析した結果、2つの新しいハプロタイプ(遺伝的型)が検出されました。
これらはどちらも「西部クラスター」に属しており、中国地方西部との連続分布があったことを示唆しています。
つまり、九州のツキノワグマは本州西部の個体群と遺伝的に近く、地理的にもつながっていた可能性が高いのです。
生息地の分断が遺伝的変異を生んだ
この研究はまた、九州と本州の間で生息地が分断された後、九州個体群に独自の遺伝的変異が生じたことも示しています。
これは孤立した島嶼環境で進化が起きた典型例であり、九州のツキノワグマが独自の系統として保全価値が高かったことを裏付けています。
1987年の“最後のクマ”は本州由来だった
1987年に大分県で捕獲された「九州最後のツキノワグマ」とされる個体は、遺伝子解析の結果、福井県〜岐阜県に分布する本州の個体群と一致。
つまり、九州産ではなく、移入されたか飼育されていた個体の可能性が高いとされています。
この結果により、九州固有のツキノワグマは1941年の記録を最後に絶滅したとする見解が強化されました。
熊の目撃情報は本当?佐賀や福岡での“出没注意”の謎
近年、九州の一部地域で「クマ出没注意」の張り紙が見られることがあります。
特に佐賀県では、2025年に「○○グマ出没注意!」という看板が話題になりました。
しかし、これらの目撃情報の多くは誤認やペットの逸出、あるいは本州から移入された個体の可能性が高いとされています。
福岡の隣県・山口ではクマの出没が相次いでおり、関門海峡を泳いで渡る可能性も専門家の間で議論されています。
とはいえ、九州本土での野生クマの定着は確認されておらず、環境省も「九州では絶滅」との立場を維持しています。
熊がいない九州の登山・キャンプ事情
熊がいないことは、九州のアウトドア愛好者にとって安心材料のひとつです。
本州や北海道ではクマ鈴やスプレーが必須ですが、九州では基本的に不要。
ただし、イノシシやマムシなど他の野生動物への注意は必要です。
まとめ:熊は九州にいつまでいたのか?そして今後は…
- 九州のツキノワグマは1940年代に絶滅したとされ、2012年に環境省が正式に絶滅宣言
- 絶滅の理由は森林伐採、狩猟、地理的孤立など複合的要因
- 近年の目撃情報は誤認や移入個体の可能性が高く、野生の定着は確認されていない
- 九州個体群は本州西部と遺伝的に近く、独自の進化を遂げていた可能性がある
熊がいないという事実は、九州の自然環境の変化を物語っています。
今後、環境保全や生態系の回復が進めば、再び熊が姿を見せる日が来るかもしれません。
しかしそれは、慎重な議論と準備が必要なテーマでもあります。