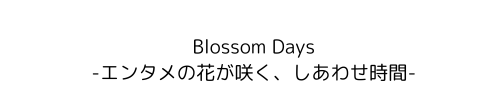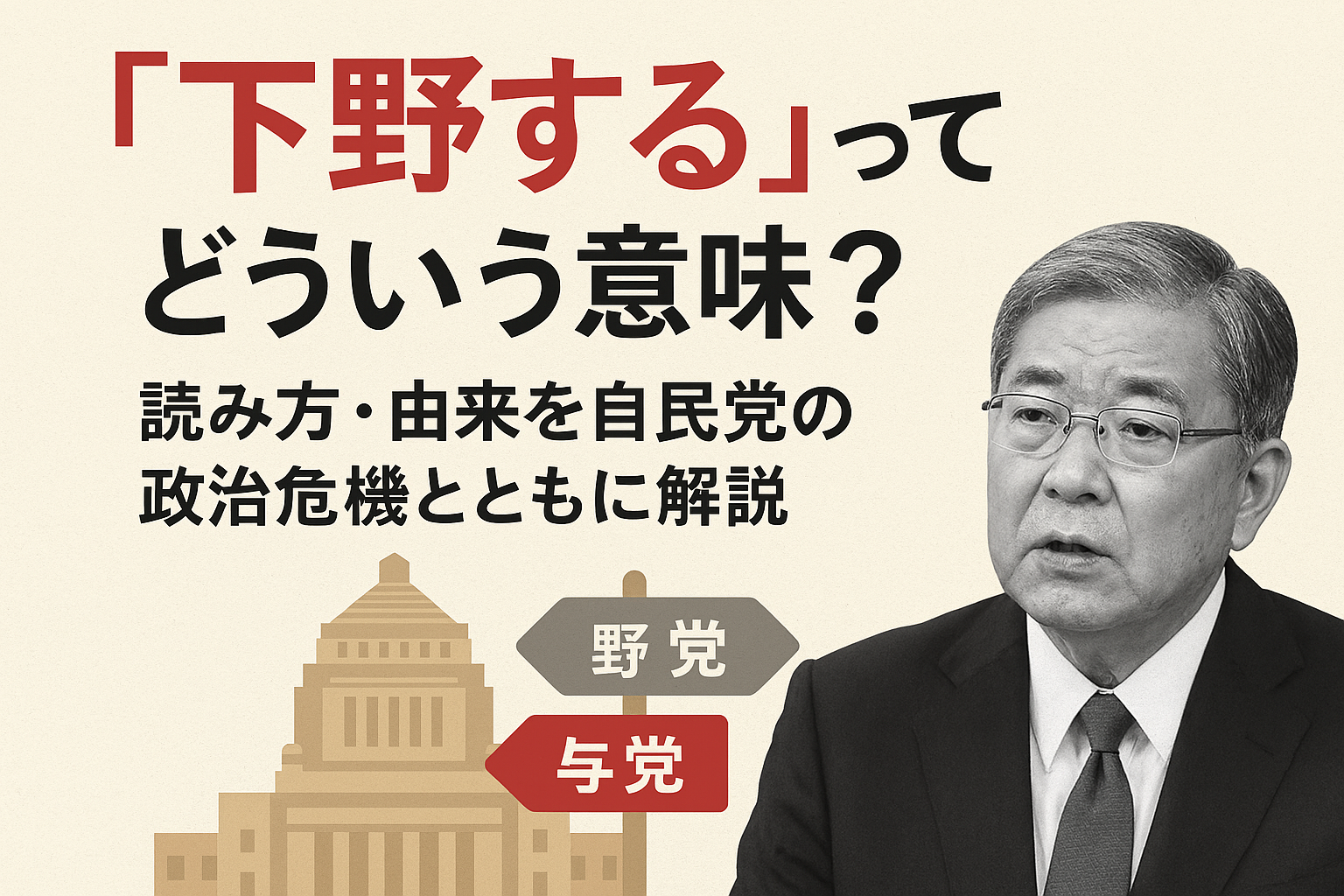※当サイトはプロモーションを含みます
「下野する」の意味と読み方とは?政治用語としての基本を解説
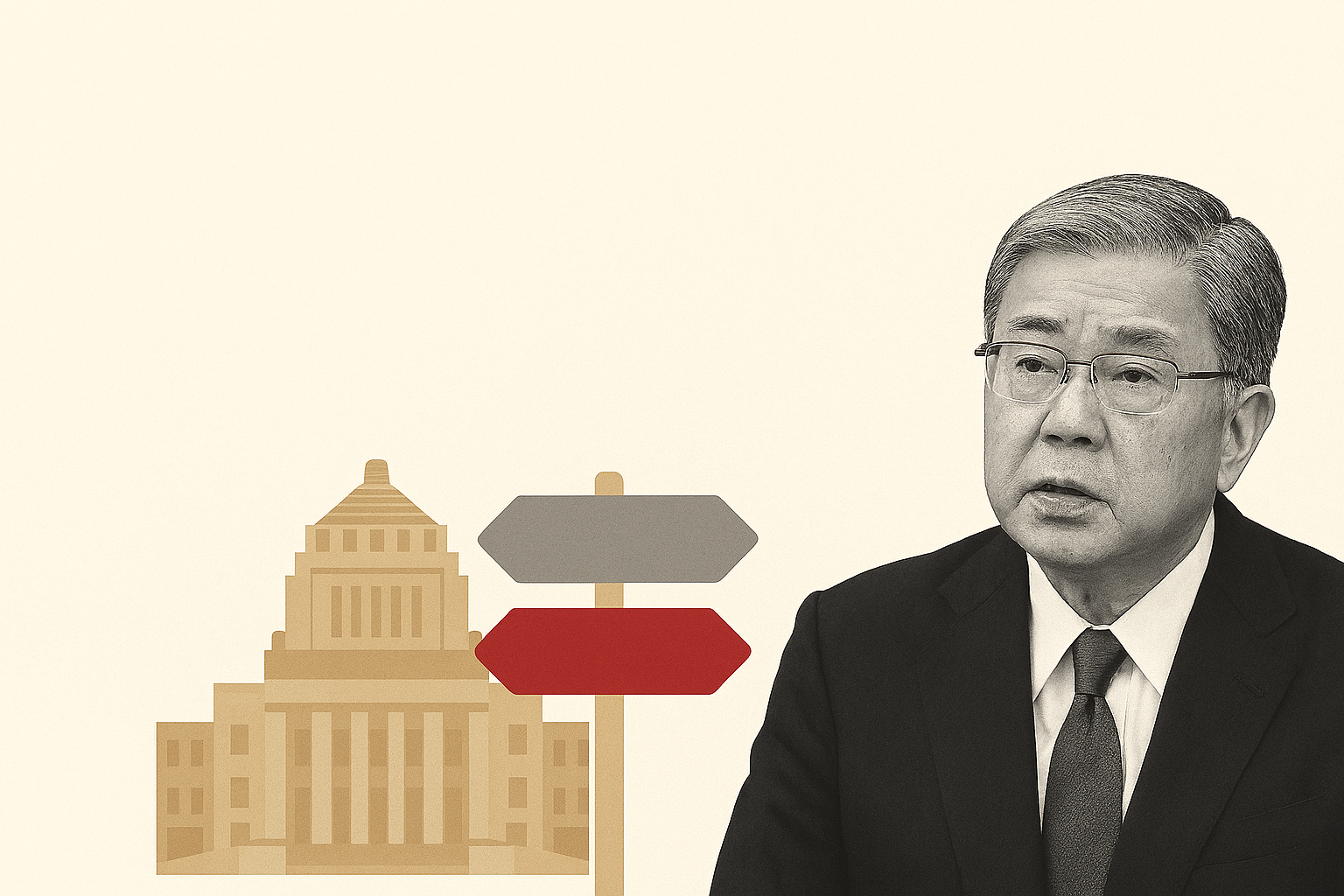
イメージ画像:Blossom Days作成
「下野する」という言葉は、政治報道や選挙後の分析記事などで頻繁に登場します。読み方は「げやする」と読み、漢字の印象からは想像しづらい難読語のひとつです。
🔸 意味
- 官職を辞して民間に下ること
- 与党が政権を失い、野党に転落すること
つまり、政治の文脈では「政権与党が敗北し、野党に戻る」ことを指します。たとえば、選挙で過半数を失った場合や、連立が崩壊した場合に「下野する」という表現が使われます。
🔸 読み方の由来
「下野(げや)」という読み方は、古語「野に下る(やにくだる)」に由来します。現代では「下野(しもつけ)」という地名もありますが、政治用語としての「げや」とは意味が異なります。
出典:コトバンク「下野(げや)」の定義より[1]
「下野する」の由来と歴史的背景|なぜこの言葉が使われるようになったのか
「下野する」という言葉の由来は、古代日本の官職制度にあります。貴族や武士が官位を辞して地方に戻ることを「野に下る」と表現していたことから、政権を離れることを「下野」と呼ぶようになりました。
🔸 歴史的な使用例
- 西郷隆盛が政争に敗れて「下野した」
- 明治期の藩主が廃藩置県後に「下野」して民間人となった
このように、政治的な敗北や引退を意味する言葉として定着していったのです。
出典:毎日ことばplus「第1486回・下野 読み方は…」より[2]
自民党の政治危機と「下野する」可能性|2025年の最新情勢
2025年現在、自民党は総裁選後の混乱と支持率低下により、「下野論」が党内外でささやかれています。特に石破茂さんが総裁に再選された後、党内の保守派と改革派の対立が激化し、政権運営に支障が出ている状況です。
🔸 最新の政治危機(2025年10月時点)
- 支持率が30%を割り込む
- 国民民主党との連立交渉が難航
- 野党(立憲民主党・日本維新の会)が共闘姿勢を強化
こうした状況の中で、萩生田光一さんや佐藤勉さんらが「一度下野して信を問うべき」と発言し、党内で「下野する」ことが現実的な選択肢として浮上しています。
出典:東洋経済オンライン「自民党内に広がる“下野論”」より[3]
1,980円
「下野する」ことの政治的意味|自民党にとってのリスクと再起の可能性
「下野する」ことは、単なる敗北ではなく、政党にとっての再起のチャンスでもあります。過去の自民党は2009年に民主党に政権を譲った際、3年後に政権奪還を果たしています。
🔸 リスク
- 政策の主導権を失う
- 党内分裂の加速
- 支持基盤の崩壊
🔸 再起の可能性
- 若手議員の台頭
- 政策の見直しと刷新
- 国民との距離を縮める機会
「下野する」ことは痛みを伴いますが、長期的には政党の体質改善や世代交代を促す契機にもなり得ます。
なぜ「下野する」が今注目されているのか?政治報道と世論の反応
SNSや報道では、「自民党は一度下野すべき」「政権交代が必要」といった声が増えています。特に若年層や都市部の有権者からは、政治の停滞に対する不満が強く、「下野する」ことへの期待も見られます。
🔸 世論の傾向
- 「長期政権による硬直化を打破してほしい」
- 「野党に一度チャンスを与えるべき」
- 「自民党は変わるために一度下野すべき」
こうした声は、単なる政権批判ではなく、政治の健全な循環を求める国民の意思とも言えます。
まとめ:「下野する」ってどういう意味?読み方・由来を自民党の政治危機とともに解説
「下野する」とは、政権を失って野党に転じることを意味する政治用語で、読み方は「げやする」。その由来は古代の官職制度にあり、現代では政党の敗北や再起の象徴として使われています。
2025年の自民党は、支持率低下と党内対立により「下野論」が現実味を帯びており、国民の間でも「一度政権交代すべき」という声が高まっています。
「下野する」ことは痛みを伴う決断ですが、政治の健全性を保つための重要なプロセスでもあります。今後の自民党の動向と、日本政治の行方に注目が集まります。