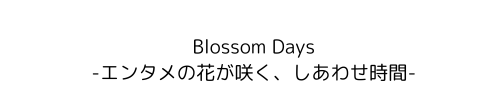※当サイトはプロモーションを含みます
はじめに:SNSで話題沸騰「無言の帰宅」とは?
2025年秋、SNS上で突如として注目を集めた言葉があります。それが「無言の帰宅」。一見すると、口をきかずに家に帰ってきた様子を表すように思えますが、実はこの言葉には深い意味が込められています。
「無言の帰宅」とは、亡くなった人が遺体となって家に戻ることを指す婉曲表現です。報道や訃報などで使われることが多く、直接的に「死亡」や「遺体」という言葉を避けるための配慮として使われてきました。
しかし、この言葉の意味を知らない人々がSNSで誤解したことで、善意のコメントが炎上を招く事態に発展しました。

イメージ画像:Blossom Days作成
「無言の帰宅」に「よかったね」──善意が招いた悲劇
ことの発端は、SNS「Threads」に投稿されたある一文でした。
「行方不明だった夫が無言の帰宅となりました」
この投稿に対し、多くのユーザーが「生きててよかった!」「今はそっとしてあげて」といった励ましのコメントを寄せました。しかし、投稿者の意図は「夫が亡くなり、遺体として帰ってきた」という悲痛な報告だったのです。
このすれ違いは、X(旧Twitter)などでも拡散され、「ホラーすぎる」「善意の地獄」といった声が相次ぎました。言葉の意味を知らないまま、文脈を読まずに反応してしまうことの怖さが浮き彫りになった瞬間でした。
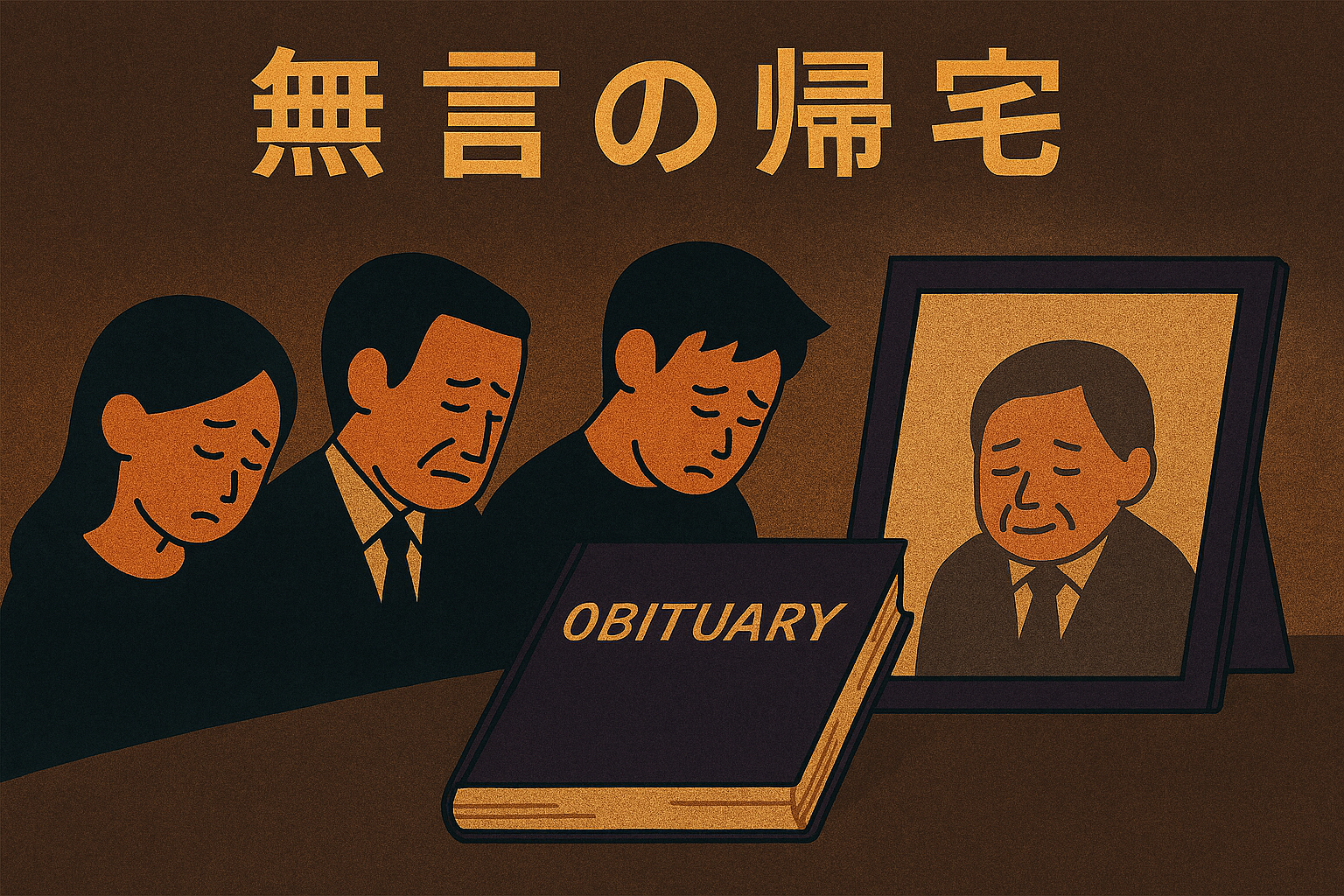
イメージ画像:Blossom Days作成
「鬼籍に入る」とは?日本語の死にまつわる婉曲表現
「鬼籍に入る」という言葉もまた、死を表す婉曲表現のひとつです。

イメージ画像:Blossom Days作成
鬼籍とは?
仏教において、亡くなった人の名前を記す帳簿を「鬼籍」と呼びます。そこに名前が記されることから、「鬼籍に入る=亡くなる」という意味になります。
この表現は、文学作品や新聞記事などでよく使われ、直接的な死の表現を避けるための美しい言い回しとして定着しています。
婉曲表現の役割──なぜ人は「死」を遠回しに語るのか?
日本語には、死に関する婉曲表現が数多く存在します。
- 鬼籍に入る
- 無言の帰宅
- 永眠する
- 旅立つ
- 静かに息を引き取る
これらの表現は、遺族や関係者への配慮、聞き手の感情への配慮、そして文化的な美意識から生まれたものです。直接的な表現が避けられることで、悲しみを和らげたり、場の空気を保ったりする効果があります。
しかし、こうした婉曲表現は、意味を知らない人にとっては誤解のもとにもなり得ます。今回の「無言の帰宅」騒動は、その典型例と言えるでしょう。
SNS時代の言葉の危うさ──文脈を読む力の低下
SNSでは、短文・即時反応が求められるため、文脈を深く読む習慣が薄れがちです。今回の騒動でも、「無言の帰宅」という言葉の前後の文脈を読まずに反応した人が多く見られました。
また、報道用語や文学的表現に触れる機会が少ない若い世代にとって、こうした婉曲表現は馴染みが薄く、誤解されやすい傾向があります。
SNSでは「意味がわかると怖い話レベル」「なんの嫌がらせか?ってなるよなぁ」といった声が上がり、言葉の意味を知る人にとっては信じがたい光景として受け止められました。

イメージ画像:Blossom Days作成
「言葉のリテラシー」が問われる時代へ
今回の騒動は、単なる言葉の誤解ではなく、「言葉のリテラシー」が問われる時代に突入したことを示しています。
- 言葉の意味を正しく理解する力
- 文脈を読む力
- 相手の立場や感情を想像する力
これらが欠けてしまうと、善意が悪意に変わり、思わぬ炎上を招くことになります。SNSでは特に、言葉の選び方が重要です。

イメージ画像:Blossom Days作成
まとめ:「鬼籍に入る」「無言の帰宅」──言葉の美しさと危うさ
「鬼籍に入る」「無言の帰宅」といった婉曲表現は、日本語の美しさを象徴する言葉です。しかし、その意味を知らないまま使ったり、反応したりすると、思わぬすれ違いや悲劇を生むことがあります。
言葉は文化であり、感情であり、時に凶器にもなります。だからこそ、私たちは言葉の意味を学び、文脈を読み、相手の気持ちを想像する力を養う必要があります。
SNS時代の今こそ、「言葉のリテラシー」を見直すべき時なのかもしれません。